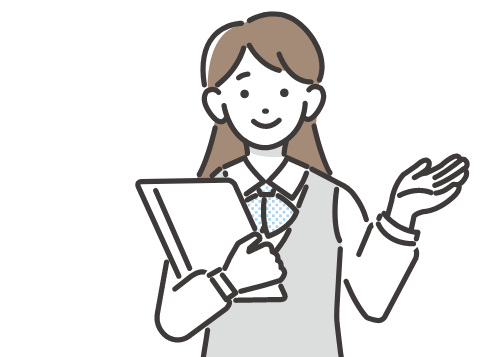導入事例一覧

内科クリニックの病院荒らしに対応する防犯カメラ導入事例
近年は小規模の内科クリニックで病院荒らしの事件が増えてきました。病院の金品や患者の荷物の置き引きなども目立ちま……
事例を詳しく見る

24時間救急対応総合病院の防犯カメラ活用&導入事例
今回導入のお手伝いをさせていただいたのは24時間救急対応の総合病院です。常に不特定多数の人が出入りするため院内……
事例を詳しく見る

動物病院で業務管理&動物モニタリングで防犯カメラの導入事例
動物病院では従業員の業務管理のほか、預かっている動物のモニタリングでも防犯カメラを活用できます。今回導入のお手……
事例を詳しく見る

コンビニで複数店舗管理&モニタリングで防犯カメラの導入事例
コンビニのフランチャイズのオーナーから防犯カメラ導入のご依頼をいただきました。今回の店舗オーナーはコンビニを複……
事例を詳しく見る

フィットネスジムで接客管理や事故対策の防犯カメラ導入の事例
フィットネスジムも昨今は競争が激化し、各運営会社はこれまで以上のレベル高い接客が求められます。また、フィットネ……
事例を詳しく見る

中古車販売店で夜間の侵入・盗難対策で遠隔監視&音声撃退防犯カメラを導入した事例
中古車販売店では以前より不審者の侵入による車両の盗難被害が後を絶ちません。1台盗まれるだけでも被害額は甚大とな……
事例を詳しく見る

レストランで店舗内外のセキュリティ対策に防犯カメラを導入した事例
レストランでは主に駐車場・接客管理・店舗内外の防犯対策といったセキュリティ管理が必要となります。ここではレスト……
事例を詳しく見る

アパレルショップで盗難&内部不正防止の防犯カメラを導入した事例
アパレルショップでは服飾品の盗難や内部不正が多発します。ロス率が高いと店舗の存続にも関わる事案のため早急に解決……
事例を詳しく見る

公園・ビジターセンターの施設に遠隔監視型防犯カメラを導入した事例
全国の公園やビジターセンターといった施設は公共団体が運営していますが、近年は防犯対策の強化に迫られる事案が増え……
事例を詳しく見る

美術館に赤外線検知&音声機能搭載の防犯カメラを導入した事例
美術館は大変高価かつ基調な芸術品が展示されているため、窃盗やいたずらから作品を守らなければなりません。そのため……
事例を詳しく見る

公民館の施設にワイヤレス防犯カメラを導入した事例
自治体が運営する公民館は地域住民が安心して利用できるよう、危機管理対策が必須となります。近年は犯罪の凶悪化が目……
事例を詳しく見る

介護施設/福祉施設で安全対策を目的とした防犯カメラの活用・導入事例
介護施設/福祉施設(老人ホーム)では利用者の安全対策の強化が日ごろ必要となります。場合によっては想定できないト……
事例を詳しく見る
 0120-210-306
0120-210-306