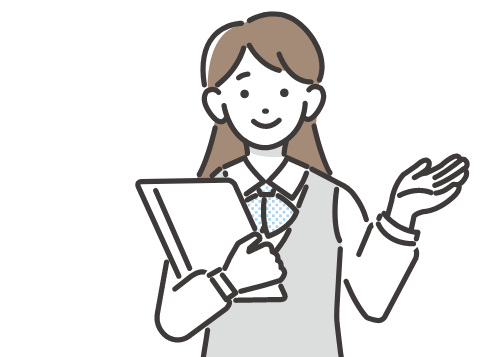屋外防犯カメラの撮影距離・範囲と注意点や選び方を解説
屋外防犯カメラを設置する際は、対象物までの撮影距離や撮影範囲を自社で検討した上で、設置環境に適した機種を選び、正しく運用しなければなりません。
そこで、ここでは防犯カメラの撮影距離や範囲を鑑みた上での注意点や選び方を解説します。
屋外防犯カメラの一般的な撮影距離

企業が設置する屋外向け防犯カメラの一般的な撮影距離は2~12m程度となります。レンズの性能や種類によって異なりますが、往々にしてそれほど遠くの被写体を撮影することは想定していない機種がほとんどとなります。
ただし、レンズの中にバリフォーカルレンズと呼ばれる変倍レンズを内蔵した防犯カメラもあり、こちらを導入することによってズームによる調整が可能となります。
バリフォーカルレンズは設置後に変倍して撮影範囲を変えられるので非常に便利ですが、当該レンズを採用している屋外防犯カメラの種類はそれほど多くないので、自社の運用にマッチした機種を見つけるのは少々苦労するかもしれません。
防犯カメラの撮影範囲と画角とは

防犯カメラの撮影範囲は焦点距離で決まります。防犯カメラのレンズも一眼レフやミラーレスカメラと同様に「f=〇mm」という表記で表されます。〇mmの値が小さいほど画角が広くなり、広い範囲を映すことができます。
一昔前のアナログ世代の防犯カメラは本体とレンズが別々だったため、設置後にレンズを交換することもできましたが、現在主流のネットワークカメラのほとんどはレンズ一体型となっているため、導入後のレンズ交換はできません。
そのため、どのくらいの撮影範囲を望むかは導入前に自社で決めなければなりませんので、運用目的をよく吟味する必要があります。
屋外防犯カメラの機種によってレンズが異なる。選び方

上記でも触れましたが、防犯カメラの撮影距離や撮影範囲は本体に内蔵されている「レンズ」によって異なります。一見すると「とにかく広い範囲を撮影できる機種を選べばいいのでは?」と考えてしまいがちですが、広角・標準・望遠レンズはそれぞれ得手不得手があるので、レンズごとの特徴を押さえた上で適切なレンズを選択しなければなりません。
広角レンズの特徴。メリットとデメリット
広角レンズは画角が広く、広い範囲にわたって撮影できるのが特徴です。一般的には4mm以下のレンズを広角と呼ぶことが多く、2.5mmでおよそ130度の視野角となります。広角であれば広範囲をカバーできるため、その分設置台数を抑えることができます。
ただし、広角レンズは近くの物体も遠くに映ってしまうので標準レンズと比較すると犯人の顔や車両のナンバープレートなどがどこまで鮮明に映せるか、といった問題が浮上します。また、画角が広いと魚の目レンズのように両端が丸みを帯びてしまい、リアルな現場の映像を再現するのが難しいこともデメリットとして挙げられます。
標準レンズ(準望遠)の特徴。メリットとデメリット
標準レンズ(準望遠)は一般的なレンズとなり、4~6mmを指すことが多く、画角は30~90度となります。70度以上のレンズは望遠と呼ばれます。標準レンズは撮影距離・範囲・画質ともに安定しており、最も企業で導入されているレンズです。
目立ったデメリットは見受けられませんが、カメラ一台でカバーできる範囲はそれほど広くないため、シチュエーションによっては複数台の設置が望ましいかもしれません。
また、上記では4~6mmを標準レンズと定義しましたが、販売店や担当者によって考え方は異なるので、「思った以上に広角だった」とならないためにも、ロケテストは必須です。
望遠レンズ(ズームレンズ)の特徴。メリットとデメリット
望遠レンズ(ズームレンズ)は5mm以上のレンズを指すことが多いです。5~50mmが一般的で、バリフォーカルレンズもこの範囲内が普通です。一眼レフカメラだと標準レンズの範囲内ですが、防犯カメラでは望遠レンズの括りとなることに注意してください。
望遠レンズは遠くの対象物をズームして撮影することができる反面、視野角が狭くなるので、カメラ回りが死角になることが多いため設置場所を吟味しなければなりません。
例えば駐車場のゲート傍や出入り口付近であれば、多少高所に設置してもナンバープレートや人の顔を撮影することはできるでしょう。
赤外線カメラを選ぶときの注意点。撮影距離を考える

また、赤外線カメラを運用する際は、撮影距離と範囲を考慮するのと同時に、赤外線の照射距離も頭に入れておく必要があります。防犯カメラの一般的な撮影距離は上述したように2~12mが目安となりますが、赤外線の照射距離は5~30mほどで、最新機種であれば50m前後届くものもあります。
しかし、赤外線を撮影可能距離以上に照射しても夜間撮影は困難ですし、単なるオーバースペックとなる可能性が高いです。防犯カメラとレンズは一体型が現在の主流なので、後から人感センサーの照射距離に併せてレンズを交換することもできません。
屋外防犯カメラの撮影距離と範囲の決め方

企業が屋外防犯カメラの設置を計画する場合、撮影距離や範囲どのように決めればいいのでしょうか。既に防犯カメラを導入しており、今回は入れ替え、という企業も今一度犯罪リスクを再度確認し、最新の犯罪に対応した撮影距離と範囲を見直してみるといいでしょう。
防犯カメラの範囲は設置台数で決める
防犯カメラの撮影範囲と本体の設置台数は密接な関係を持ちます。
既に導入したい防犯カメラの機種が決まっている場合は、そのカメラレンズでカバーできる範囲から設置台数を計算することもできますし、その逆で最初に防犯カメラの設置場所と台数を決めたのち、どこまでの範囲をカバーするかを決めることもできます。
例えば幅100mの範囲を撮影したい場合、まず考えるべきは導入予定のカメラが1台で端から端まで何メートル撮影できるかを確認します。右端から左端までの距離を「水平距離」と呼びますが、設置予定の防犯カメラの水平距離が15mの場合は、100m÷15m=6.666となり、100mの範囲をカバーするためには単純計算で6~7台必要となります。
隣家などプライバシーを配慮した画角・範囲か
防犯カメラの設置場所が企業の敷地内に留まらず、公共施設や公道、隣家などにレンズが向いている場合、近所からクレームが来る可能性もあります。防犯カメラを設置する目的は犯罪抑止となりますが、中には「監視されているようで気味が悪い」とプライバシーの侵害を訴える人も出てくるかもしれません。
そのため、極力防犯カメラのレンズは公道から見えないようにするとともに、場合によっては「防犯カメラ作動中」といった看板を傍に設置することも検討するといいでしょう。
どこまでの距離まで鮮明な画質の撮影が必要か
カタログスペックを確認したり、販売店の担当者からは「30m先まで鮮明に映すことができますよ」と提案されても、実際に運用してみると、30m先では画像が粗く不審者の顔やナンバープレートなど特徴を捉えることができないこともあります。
「鮮明な画像・高画質」という言葉は人によって実際の印象が異なるため、言葉通りに信用してしまうと危険な場合があります。夜間撮影における画像の鮮明さは、防犯カメラの赤外線技術とイメージセンサーのサイズ・性能が重要となるので、機種の選定から販売店の専門家に意見を貰うのがいいでしょう。
まとめ:屋外防犯カメラの機種選定は目的を考えて計画的に
今回は防犯カメラの屋外使用における撮影距離や撮影範囲を解説するとともに、機種・機能の選定方法を紹介しました。防犯カメラは配線工事などが必要となるため、簡単に設置場所を変更したり機種を交換することができません。
そのため、防犯カメラの導入・買い替えを検討している時点から信頼できる販売店を見つけて、相談してみるのがおすすめです。当サイト「防犯カメラナビ」では、問い合わせをいただいた後、無料で現場調査、及びロケテストの実施が可能です。
是非一度お問い合わせください。
 0120-210-306
0120-210-306