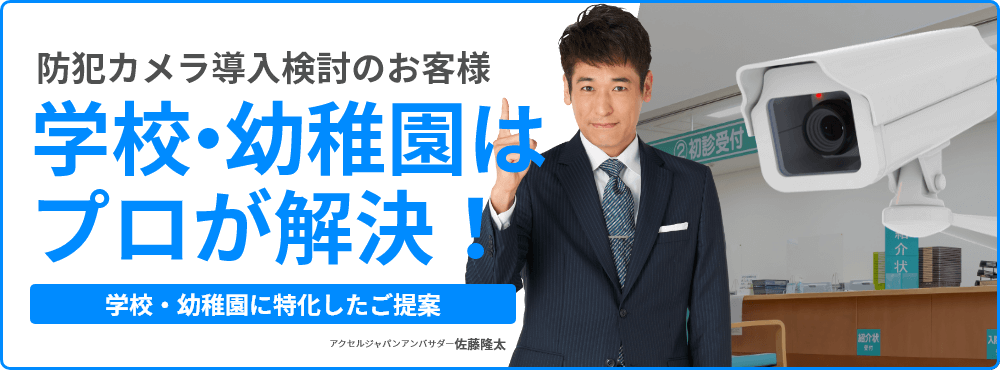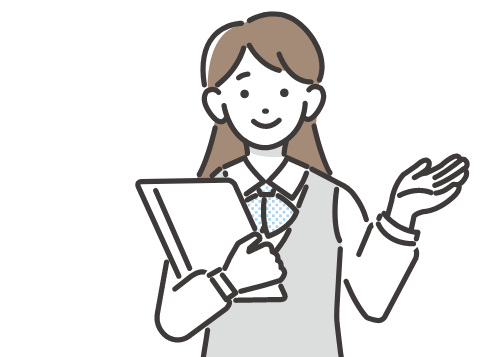学校・幼稚園で怪我やトラブルの証拠をしっかり確保!最新の対策方法を紹介
学校・幼稚園では、児童や園児が教員の目を離した隙に、思わぬ怪我を負ってしまうことがよくあります。何事もなく済めばいいのですが、怪我の具合やトラブルの原因によっては、子供の親が出てきて、教育員会まで巻き込む大きな問題に発展するケースもあります。
昨今は学校・幼稚園もDX化が進み、あらゆる面でデジタル化が浸透しはじめています。児童や園児の怪我・トラブルは、「言った言わない」、「やったやらない」と不毛なやりとりが延々と続くケースが多いため、証拠を確保して問題解決を図ることをおすすめします。
今回は学校・幼稚園内で発生する怪我やトラブルの証拠の確保を目的とした、最新の防犯対策をご紹介します。
学校・幼稚園で多発する子供の怪我やトラブル
学校・幼稚園といった大勢の児童・園児を預かる場所では、多かれ少なかれ子供が怪我をしたり、トラブルに巻き込まれる事故が発生します。学校・幼稚園側はすべてを未然に食い止めることはできませんが、想定されるトラブルに関しては、事前に手を打つことで問題が大きくなる前に対処・解決を図ることができます。
遊具関連の怪我・トラブル
取り分け多発傾向にあるのが幼稚園における遊具を原因とした事故・怪我です。遊具の中でも事故率が高いのは「すべり台」、「アスレチック」、「鉄棒」の3箇所で、保育所と合わせて年間6万件以上の事故が報告されています。事故として扱われない軽傷なども含めれば、その数は何倍にものぼることでしょう。
すべり台やアスレチックなどは高い場所から落ちてしまうと大怪我を負うリスクがあるので、教員がしっかりと園児を管理しなければなりません。また、過去にはビニールプールで園児が遊んでいる間、教員が3分ほど目を離した隙に、園児が原因不明の溺死をした事故がありました。教員には監督義務違反として遺族に3400万円の支払いが命じられました。
子供同士の遊びや喧嘩による怪我
子供同士が遊んでいる最中に、ふとしたことで喧嘩に発展することは頻繁にあります。お互いが感情的になって、言った言わない論争を繰り広げるため、証拠となる映像がない限り、問題の解決は困難となります。万一児童・園児が怪我を負ってしまった場合、親が介入し、事実関係が分からぬまま相手の子供や親に激怒したり、学校側にクレームや慰謝料を要求することもあります。
学校・幼稚園の教員と園児のトラブル
園児はそのときの気分次第で平気で嘘を言うことがあります。実際は園児の行動に注意をしただけにも関わらず、親には「先生にぶたれた」と嘘を言い、親がクレームに乗り出すこともあります。
音声付きの録画映像があれば、証拠として親に確認してもらうことも可能ですが、それがかなわない場合、多くのケースでは学校・幼稚園側が謝罪をすることになります。
学校・幼稚園で怪我やトラブル時に証拠がない場合
学校・幼稚園では怪我やトラブルは必ず多発します。そのため、教員側も「事故は必ず起こるものだ」という認識で対策を講じなければなりません。
上記のようなトラブルは何かしらの証拠があれば、問題が大きくなる前に解決を図ることができますが、その一方で証拠がない場合は、学校・幼稚園側も止める術をもちません。
親のクレームに対応できない
親は往々にして子供の怪我に敏感です。学校・幼稚園でいじめや事故があれば見過ごすことはできませんし、教員に対して強く対応を求めます。しかし、教員は1クラス最大で35人の児童・園児を管理しなければなりませんので、死角で見えない場所で事故が発生したり、すべり台から足を滑らせて落ちてしまったりなど、その場で監視しても防げないトラブルもあります。
しかし、録画映像がなければ、そのトラブルを本当に防ぐことができなかったのかどうかが分かりません。証拠がないうちは親のクレームに対して言い返しても、平行線を辿るだけとなりますので、親と教員との良好な関係構築は遠のく一方となります。
教育委員会から調査が入る
公立幼稚園で何かトラブルが遭った際は、基本は市の学校教育課に問題提起をするのが流れとなりますが、子供を学校・幼稚園に預けている多くの親は、「クレーム=教育委員会」と考える傾向があります。クレームをする親の中には、何が真実なのかよくわからないまま、子供の言い分を鵜呑みにして、学校・幼稚園の対応を批判します。そのため、場合によっては教育委員会も本格的に調査をすることになります。
学校・幼稚園で怪我やトラブル時に証拠がある場合は対応が大きく変わる
上記のような問題は、学校・幼稚園に防犯カメラを設置することで、事故発生時は録画映像を証拠として確認することができます。不審者の侵入に対する防犯対策にもなりますので、未だ設置をしていない学校・幼稚園は、本格的に検討してみてはいかがでしょうか。
 0120-210-306
0120-210-306