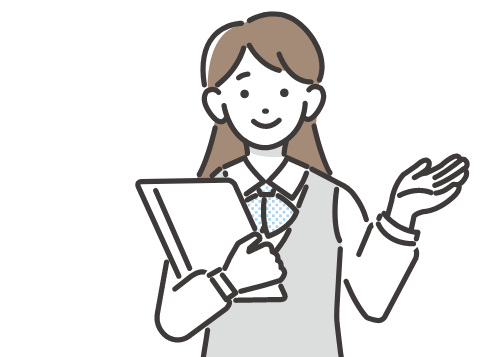福祉施設・介護施設の防犯カメラは補助金申請で導入できる
福祉施設・介護施設でも昨今は防犯カメラの導入が推奨されています。「そんなこと言っても予算が取れないよ」という施設も多いことでしょうが、あらゆる介護・養護施設では、政府や自治体が実施する補助金に申請することによって、導入費用の大半を賄うことができます。
しかし、申請にあたっては注意点も多々あります。ここでは補助金申請の条件や注意点をご紹介します。
全国の福祉施設・介護施設は防犯カメラの設置が必要

近年、福祉施設・介護施設は地域問わず、防犯カメラなどのセキュリティ対策が求められています。すでに多くの施設で導入が進んでいますが、「そうはいっても予算が取れない」という福祉施設もいまだ多くあるようです。
しかし、昨今の犯罪情勢を鑑みると、もはや防犯カメラの導入は必須となり、導入していない福祉施設・介護施設に関しては、入居者・職員の十分な安全対策が講じられていないとみなされる傾向にあります。
近年は犯罪の凶悪化が際立つ
近年は犯罪の凶悪化が目立ち、福祉施設・介護施設に侵入した男が入居者や職員に対して凶器を振り回す事件も報じられました。施設ではカラーボールやさすまたなど犯罪者に立ち向かうセキュリティグッズを常備しているところもありますが、刃物を振り回している相手に、本当に一般人が扱うことはできるのでしょうか。
防犯カメラの設置はこのような犯罪者の侵入を未然に防ぐためであり、福祉施設・介護施設の外周りで不審者を発見し、敷地に踏み込ませないための手段となります。
入居者を守る。職員の勤務状況を管理
上記では犯罪抑止を防犯カメラの設置例として挙げましたが、福祉施設・介護施設では、室内に設置することによって入居者を24時間守ることができます。また、昨今は職員が入居者に暴行するニュースも話題となっていますが、そのような事件が起きないように、職員の勤務状況を管理することも防犯カメラでは可能となります。
防犯カメラと言えば、事件や事故のあとの証拠映像の確保の役目というイメージを持っている人が多いですが、実はそうではなく、防犯カメラの導入の本質は、事件・事故を未然に防ぐためとなります。
福祉施設・介護施設は補助金で防犯カメラを設置できる

しかし、防犯カメラの導入にあたって最もネックとなるのが「予算」です。福祉施設・介護施設の玄関や敷地内外に複数台設置する場合は、規模によっては100万円を超えることもあります。慢性的な予算不足の福祉施設・介護施設にとっては、かなり導入のハードルが高い価格帯となるでしょう。
しかし、近年は安全なまちづくりを推進するため、政府や自治体が積極的に防犯対策における補助金・助成金を打ち出しています。補助金・助成金は民間企業ではなかなか申請条件に合いませんが、福祉施設・介護施設であれば、大抵が申請できます。
福祉施設・介護施設は最大で4分3の補助金が下りる!
防犯カメラの導入は上述したように高額になりがちですが、福祉施設・介護施設が申請できる補助金は、最大で4分3の補助額となり、ほとんどの導入費用を賄うことができます。
ただし、注意点としては、実際の補助額はその時の補助金制度によって異なります。また、防犯カメラの補助金の中には「新規で導入する補助金」と「すでに導入済の防犯カメラの買い替えやメンテナンス費用、修繕費用に対する補助金」に区別されることが多いため、各福祉施設・介護施設は、自分たちがどの補助金を申請できるのか、しっかりと要綱を確認しなければなりません。
福祉施設・介護施設が補助金を申請できる条件とは

福祉施設・介護施設が防犯カメラの導入で補助金を申請したい場合、まずは自治体のホームページ、もしくは窓口に問い合わせて、現時点で募集している補助金制度をたずねてみるといいでしょう。
福祉施設・介護施設が防犯カメラに対して申請できる補助金は、下記のような制度が一般的です。
・厚生労働省から認可されている福祉施設・介護施設の防犯対策
・福祉施設・介護施設の事故防止対策
・福祉施設・介護施設の虐待防止対策
国から認可を受けている施設かどうかも重要となりますので注意してください。
個人の自宅高齢者介護・見守りサービスで補助金は申請できる?
一方で昨今は高齢者を自宅で介護する個人宅も増え、見守りサービスも普及してきました。カメラや宅配、センサー型などいくつか種類がありますが、このような見守りサービスに対しての補助金を実施する自治体もあります。
例えば東京都葛飾区では、防犯対策の販売店を通じて設置した防犯カメラなどのセキュリティ機器の費用に対して、10分9を補助する制度があります。個人で通販サイトで購入・設置した場合は対象外となりますので注意が必要です。
このように徐々に個人に対しても補助金制度は広まっている印象はありますが、実際は「上限は1万5000円まで」と補助額は福祉施設・介護施設と比べると大幅に小さな額であることがほとんどです。
福祉施設・介護施設が防犯カメラの補助金を受ける注意点

福祉施設・介護施設が防犯カメラの補助金を申請する際は、幾つかの注意点があります。場合によっては補助金が却下され、受け取った金額の返還義務を負う可能性もあります。
市区町村によって補助金の対象・補助額・条件は異なる
上記でも触れましたが、防犯カメラに対して補助金を申請できる制度の内容は市区町村・自治体によって大きく異なります。また、政府の補助金制度であっても、毎年実施されるとは限りませんし、昨年と同じ補助金制度の名称であっても、補助額や申請条件が大きく変更されることもよくあります。
補助金は「条件さえクリアできれば、どの福祉施設・介護施設も補助金が通る」というものではありません。政府・自治体は補助金制度毎に予算を持っており、基本は募集を開始すると、すぐに予算限度を超えてしまうので、福祉施設・介護施設の中には申請しても通らないこともよくあります。
福祉施設・介護施設は遂行責任がある。適切な防犯カメラの使用を
近年は補助金制度を悪用した悪質な企業も多く、政府自治体もそのような企業の排除に乗り出しています。補助金を受け取った福祉施設・介護施設は定期的に導入後の報告が必要となり、場合によってはしっかりと防犯カメラが業務に活かされているか、自治体職員が抜き打ち検査をすることもあります。
このように、補助金で防犯カメラを導入した福祉施設・介護施設には遂行責任があり、もし防犯カメラを適切に設置・運用していなかった場合は、法律の下により補助金の返還義務が生じます。
補助金は国の国庫や自治体の予算といった市民の血税から支払われていることを忘れないようにしましょう。
防犯カメラの補助金申請は複雑多岐!専門の販売店に相談を

防犯カメラの補助金申請条件をクリアした福祉施設・介護施設は、さっそく補助金の申請書類を準備しなければなりませんが、実はこれが複雑多岐にわたり非常に厄介です。
しかも補助金の申請期間は非常に短く、1~6か月程度しかありません。補助金の募集が開始されてもすぐには気づきませんので、大抵は申請期限まで残り1~2か月程度のところで慌てて申請書類を作成・準備することになります。
しかし、これまで自分たちで申請したことがない福祉施設・介護施設の担当者はスムーズに書類を準備することはできません。
そのため、補助金を申請することが決まった段階で、なるべく早く防犯カメラの販売店に相談して、一緒に書類を準備してもらうのが最善となります。
まとめ:福祉施設・介護施設は補助金で最新のセキュリティ対策を

福祉施設・介護施設には弱者となる入居者が大勢います。定期的に犯罪者が侵入したときを想定したマニュアルの確認や訓練も実施していることかと思いますが、実際はうまくいくかは定かではありません。
そのため、全国の福祉施設・介護施設の担当者は、事件や事故を未然に防ぐ手立てを検討するのが先決と言えます。防犯カメラの導入の際は、是非補助金を有効活用してください。
 0120-210-306
0120-210-306